改訂版 新・スラム街の少女 ―灼熱の思いは野に消えて― 第二十七話 「第10章 灼熱の思いは野に消えて」
愛は国境を越えてやってきた。
不思議な力を持つスラム街の少女プンとともに、 日本人駐在員は愛と友情をかけて、 マフィアと闘う。
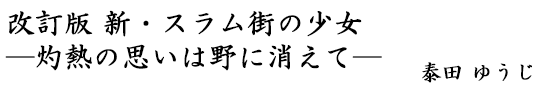
第10章 灼熱の思いは野に消えて
シーアとクンは、ウドムスック近くのバンナーの高速入口から高速道路にのり、ドンムアン空港方面に向かった。
「どこに行くの?」
「しばらくアユタヤにでも行くか」
「あんたの田舎アユタヤなの?」
「俺に田舎なんかねえよ」
アユタヤへはドンムワン空港近くの高速出口からバンパイン方面の一般道路を走っていく。
シーアは両腕に刺青をしている。車を走らせながら自分の腕の汗が太陽できらきら光るのを見た。
そっくりの腕だ。シーアは夢に何度も出てくるシーンを思い出した。
鉄屑の入ったリヤカーの後ろに座っていた。親父は工場の跡地で鉄くずを拾い集めている。
太陽の光が鉄に当たり反射する熱でリヤカー内は、40度を超えていただろう。俺は四歳か五歳くらいだったのだろう、正確にはわからない。
お袋は数日前からいなくなっていた。どんなお袋だったか、顔を思い出せない。
夜、お袋に抱かれて寝た温かみだけがわずかに思い出される。
暑くて、腹が減って、喉が渇いて、俺は泣き出した。
「おなかがちゅいたよ。のどもカラカラ、お水ちょうだい」
親父は黙ってリヤカーを引いた。俺は泣き続けていた。
橋にさしかかるとリヤカーを止め、周りに誰もいないのを確認する。
親父がリヤカーの後ろにやってきた。
手が伸びてくる。
腕の汗が太陽できらきら光っている。
親父は俺を抱えあげ、川に落とそうとした。
俺は必死で親父の腕にしがみついた。
「おなかちゅいてない、ちゅいてない」
親父は振り払うようにして俺を川へ投げ捨てた。
必死で水の中でもがいた。もがけばもがくほど沈んでいく。水の中で意識はだんだん遠ざかっていった。
川岸に打ち上げられた俺を拾って帰ったのは、トンブリにある売春宿の主人だった。
そこには10代~20代前半の若い女の子が働いている。女の子はカンボジア国境付近の難民やイサーン地方(東北地方)の農家出身がほとんどだ。売春宿の主人が僅かな値段(5000バーツ~)で買ってきた女の子だ。
女の子たちは、寝る時間を除いて客をとらされる。
生理の時を除き、まるまる一週間働く。休日は年末年始の2日だけだ。
人気のある子は1日20人以上の客をとる。トンブリ地区は、外人は住んでいない。
客のほとんどがタイ人。一回の値段は300バーツ。
3年間は、女の子には飯が与えられるだけで客のチップだけが収入源となる。
3年~5年働くと自由になる。稼いだ金の1/3が自分の手元に残るようになる。
売春宿を出て行っても良い。が、なかなか出て行けなくなっている。
世間を知らない。右も左もわからない。世間も受けつけてくれない。身元の保証がないので働き口がない。
たいていの女の子たちは、身体がボロボロになって働けなくなるか、エイズにかかるまで働く。
幼い体で稼いだお金を貧しい家族のために送る。
拾われたシーアは、売春宿の女の子の小間使いをして育った。20人の女の子の下着を洗った。
おやつのガイヤーンやソムタムを頼まれて屋台に買いに行く。
生理用品から爪きり、マ二キュアやら何でも必要なものも買いに行く。
女の子のご機嫌がいいとお駄賃に1バーツもらえるが、めったにあることじゃあない。
シーアはそこで働く女の子のストレスのはけ口になることの方が多かったのだ。
売春宿の主人の狙いだ。女の子のストレスのはけ口にシーアを飼ったのだ。
虐げられた社会では自分より惨めで劣勢な者が必要なのだ。
売春宿の女の子の多くがシーアをよくいじめた。買ってきたものの色が気にいらない。
間違えたと言われ蹴られ、のろいと言われては殴られ、返事をしないと言われては髪の毛を千切れるまで引っ張られる。
シーアにいつもやさしくしてくれる子が一人いた。
名前はファイ(火)で、12歳でコラートから買われて来た。髪を背中まで伸ばし、目の大きいきれいな子だ。3年働いて16歳だった。
ファイはシーアを見ると弟を思い出した。いつも弟を背中におぶって畑で働いた。
畑でライチの実を弟の小さな口に入れるのが楽しみだった。ファイはシーアにお金やお菓子をくれた。
シーアが九歳の頃だった。2階の廊下の奥にあるフォン(雨)の部屋に洗濯物を取りに行った。
ベッドの上にピンクのビニール製の財布が置いてあった。
トイレに行ったのかフォンはいない。スーパーで日本車のミニチュアカーが200バーツで売っている。さっき見たらピカピカに光っていた。欲しかった。
シーアは夢中で財布をパンツの中に押し込んだ。廊下に出るとフォンがトイレから戻ってくる足音がする。
急いでフォンの隣にあるファイの部屋に逃げ込んだ。ファイは一階の食堂にご飯を食べに行っていなかった。
財布が無いのに気がついたら、一番に疑われるのは自分だと思った。
ばかな事をしたと思ったがもう遅い。魔がさしたというかつい夢中でしてしまった。部屋と言っても壁があるわけではない。
天井までないベニヤ板で仕切られているだけだ。シーアは息を凝らしてじっと隣の様子を窺がった。
隣の様子が手に取るようにわかる。
フォンは騒ぎ出した。
「財布盗まれたよ」フォンは大きな声でわめきはじめた。
フォンは部屋を出て、一階の主人の部屋に走って行った。
シーアは恐くなりパンツの中から財布を取り出し、ファイのベッドの下に財布を投げ入れた。
シーアはそっとファイの部屋から出ると一階にそっと降りて行った。
主人の部屋ではフォンが泣いていた。両親にお金を送る前で、財布には2000バーツ以上入っていた。
フォンは主人に自分がトイレに行っている5分くらいの間に盗まれたに違いないと言った。
「大丈夫、今直ぐに見つかる」主人がフォンを連れて客引きの部屋に行くと、そこには化粧を直している子や雑誌を読んでいる子やおしゃべりをしている子が10人近くいた。
この部屋にどのくらいの間、居るのか主人が一人一人に聞いた。皆は30分以上前から客を待っていると答えた。
客を取っている子以外は食堂にいる。
主人とフォンは食堂に行った。そこに居た7人の女の子達にも同じような質問をした。
ファイを除いて皆、食堂でご飯を済ませていた。
運の悪いことにファイはフォンがトイレに行った後に部屋を出て、食堂に来た。まだ食事を始めたばかりであった。
主人はファイが怪しいと思った。シーアは外に居て洗濯をしている。
主人とフォンはファイを地下室に連れて行った。
いきなりファイの頬を叩き、正直に白状すれば今回は許すと主人は言った。
ファイは何を言っているのか分からない。何もしていないと泣きながら主人に訴えたが、 「お前しかいないだろ、白状しろ。自分から白状しないと見せしめのため痛い目に合わせるぞ、お前は客の人気もあるから白状すれば、今回だけは許してやる
ファイは顔を横に振った。
主人はファイの衣服をはがして裸にしたが財布は出てこない。
「フォン、ファイの部屋を見て来い」
フォンは急いで二階のファイの部屋に行った。部屋には家具らしいものはない。
ベッドの横の小さなサイドテーブルとスチールパイプのとビニールでできた衣装ケースだけだ。
サイドテーブルの引き出しを開けるとファイの家族の写真が一枚あった。両親と弟とファイの四人が写っている。フォンは写真を取り出すと破り捨てた。衣装ケースの中の洋服を全部出して調べたが何も出てこなかった。
フォンは念のためベッドの下を覗いた。
あった、大切な財布があった。小学校の時に父が買ってくれたビニールのピンクの財布だ。
財布の中を確認するとさっき数えたばかりの2千4百バーツがちゃんとあった。フォンは財布から紙幣を抜き出し、地下に行った。
地下室に入るといきなりファイの髪を掴んで引きずり倒した。
床に倒れたファイの顔を踏みつけ、 「財布がこいつの部屋にあった。でも中は抜かれて1バーツもない。どこにやった。出せよ。泥棒」
フォンは金切り声を出しながらファイの腹を蹴った。
「そうか財布は見つかったんだな」
主人はそう言うと倒れているファイの傍にしゃがみこんだ。
「嘘をついたらいけないよな。ファイ、舌を出しな。嘘を言えないようにしてやろう」ファイの顔を起こした。
ファイは恐怖で目を見開き、頭を振り、もがいた。主人は拳で顔を殴った。
「フォン、押さえていろ、鋏で舌を切ってもいいが・・・・・・」
フォンはファイの手を押さえた。主人はファイの口をこじ開け、点けた煙草の火を口の中に押し込んだ。
「うわあぁー」物凄い悲鳴があがった。
「お前のお手も悪いな」
主人は新しい煙草に火を点け、右手を押さえ敏感な指先に火を押し付けた。
ジュウっと肉が燃える音と蛋白質のこげた臭いがした。
ファイは気を失った。泣きながら気を失った。
泰田ゆうじ プロフィール 元タイ王国駐在員 著作 スラム街の少女 等 東京都新宿区生まれ |
